Interview

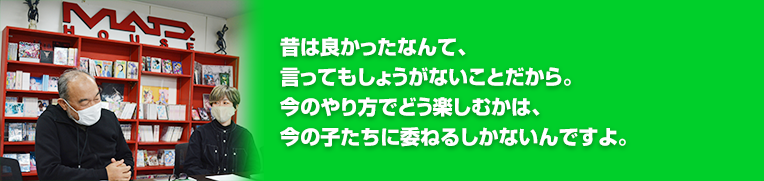
![]()
――マッドハウスは、これまで『メトロポリス』という、等身大のロボットが主人公で、かつ未来世界が舞台の作品を制作しています。また、本を正せば虫プロの流れを汲むスタジオですから、「アトムの遺伝子」との紐帯も感じるのですが。
佐藤 『メトロポリス』のしょっぱなのカットは、今見ても本当にすごいですよ。僕なんか作画出身だから、アニメで見たことがない映像をインパクトにする作り方がどれだけ難しいかわかるんです。全然違うと思いますね。
芦川 でも逆に『メトロポリス』を見た経験があるから、この作品はちょっと違う方向にしようみたいな感じはありましたよね。
佐藤 そうだね。
芦川 原作は、リアルな現在にある技術の裏付けがあっての漫画だったので、地に足が着いた感じだなと。だから未来の街についても、原作漫画だと世界を見せるような描写があまりないんですよ。個人個人のお話が積み重なっているので。ただ、だからこそ、そこに関してはアニメで佐藤監督が頭を悩ませていて。
佐藤 そう。世界を見せる描写が原作にないんです……。でも、アニメだと繋ぎでどうしてもそういうショットを入れないといけなくて。なので、『AI』ではそういった背景美術を、スペシャルな方々に描いてもらったんですよ。パッと引いて全景を見せた時に、「あっ、今の日本じゃないんだな」とチラ見せするだけでも、未来感は出せるんです。その対比として、そのなかで起きているドラマと生活感は、今とほぼ変わらないとしたかった。
芦川 「150年後の未来はどうなっていてほしいですか?」みたいなところで、美術の方と色々相談しました。ソーラーパネルが主流になっているのか、といった話をしましたね。
――今少し美術の話が出ましたけど、美術ボードとして河野(羚)さんが立たれていますよね。マッドハウスでは湯浅監督作品などで何度かお仕事をされてますが、佐藤監督と組まれるのは初めてなのでは。
芦川 そうですね。今までの作品と変えていることとして、監督とまだ組んだことのないスタッフの方に、とは思っていたんです。ダメだったからではなくて、これまでの佐藤監督と違う系統の作品だったので。美術も綺麗な方向で、キャラクターもシンプルな漫画っぽい感じで。そういう原作をもらったときに、新しいスタッフとも組めるなと。
河野さんは美術ボードをやっていただいて、美術設定も今回田中(涼)さんと監修で矢内(京子)さんという方が立たれていて、実写系の方なんですよ。
佐藤 最初に、引いたイメージボード的なものを、自分がたくさん描いたんです。それに対して、清水さんがコンテでグレードをあげてくれて、なおかつスペシャルな人が描いてくれて背景にしてくれた。久々に描き込んである背景にお目にかかりましたね(笑)。
芦川 河野さんに「綺麗な世界観にしたいんです」と。その前提でボードを描いてもらって。
――ハッとさせるカットがいくつもありました。
芦川 そう言っていただけると嬉しいです。
佐藤 最近はアクション作品がいっぱいあるけど、そういうのとは切り口が全く違うタイプだから。
芦川 『カイジ』をやったときも、アクションとは別の切り口……心理ドラマでの方向での演出を確立されていらっしゃったので。
佐藤 アクションものを自分に振ったことないもんね(笑)。
芦川 振りたくないわけじゃないですよ!(笑)。私は、アクションをしていれば面白いと思ってないので。お話あってのアクションなので。
佐藤 確かにね。でも、マッドも力のある会社なんで、できないわけではないんです。他のプロデューサーさんは、アクションバリバリのものをやったりもしていますからね。ただ、それをやりたいかどうかはまた別だから。特に芦川はドラマがしっかりしているものを作りたがるんですよ。
